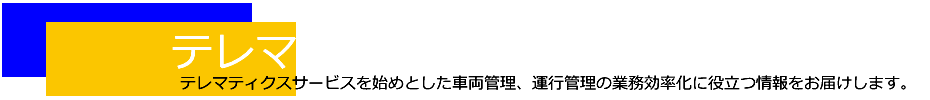2024年11月1日に道路交通法が改正され自転車のながら運転・飲酒運転が厳罰化されました。
施行から1ヶ月以上が経過しましたが、世間ではまだまだ知らない方も多いようです。
年末年始など、お酒を飲む機会も増えてきますので、この機会に是非変更のポイントを押さえておきましょう。
法改正の背景
1.法改正の背景
近年、自転車は環境にやさしい移動手段として、また健康志向の高まりから通勤・通学やレジャーでの利用が増加しています。しかし、その一方で自転車関連の交通事故も増加傾向にあり、社会問題となっています。
警察庁の統計によると、2023年の自転車関連事故は72,339件で、前年と比べて2,354件も増加しました。特に注目すべき点は、全交通事故に占める自転車関連事故の割合が2割を超えており、2021年以降、増加傾向が続いているということです。
重大な事故につながる可能性が高くないことから、自転車の交通違反は比較的見逃されることが多かったのですが、近年の事故増加の影響もあり自転車に対する社会の目は年々厳しさを増しています。
自転車は法律の定めに照らすと「軽車両」に該当しますので、当然道路交通法の規制対象となります。
2017年には川崎で自転車による死亡事故が起きています。
20歳の女子大生が右手に飲み物、左手にスマホを持った状態でイヤホンをしながら電動アシスト自転車を運転し、77歳の歩行者にぶつかり死亡させたこの事故は、ニュースでも大きく取り上げられました。
歩行者もスマホを見ながら歩く人が増えてきていますが、「軽車両」である自転車の運転でも同様に「ながら運転」が増えることにより、重大な事故が増えています。
このような世間の流れから、警察では自転車のながら運転や酒気帯び運転の厳罰化に踏み切ったと考えられます。
自転車の場合運転に免許が必要ないため軽く考えてしまいがちですが、悪質な違反の場合には刑罰が下されることもあるので注意しましょう。
自転車は歩行者の仲間ではなく、車両の仲間です。
なお、自転車の交通違反の場合、自転車指導警告カードの交付が行われます。
軽い違反ですと注意だけで済まされたり、自転車指導警告カードを交付されるだけで、カードが累積したからといってペナルティーはありません。
ただし、だからといって違反行為を繰り返してはいけません。一度でも警告カードの交付を受けたら、しっかりと自分の運転を反省して、今後は交通ルールを守るようにしましょう。
悪質な違反については、自転車でも「赤切符」で処理されることになります。
赤切符は、刑事責任を問うために事件として扱うものです。反則金を支払い、刑事処分を免れるといった手続きはできないため、刑事裁判で裁かれ、刑罰を受けることになります。
2024年11月からの変更点
2.2024年11月からの変更点
特に重大な事故につながる可能性のある以下の違反行為が重点的な取り締まりの対象となります:
【令和6年(2024年)11月からの罰則内容】
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
・6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
【自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合】
・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則】
今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となりました。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
【酒気帯び運転】
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合】
・自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合】
・酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合】
・同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

まとめ
2024年11月から始まる法改正を皮切りに、自転車運転に関するルールは段階的に厳格化されていきます。特に2026年からの青切符制度の導入は、自転車運転に対する社会の認識を大きく変える転換点となるでしょう。
個人利用者はもちろん、事業者の方々も、これらの変更に適切に対応していく必要があります。自転車は便利な交通手段である一方で、使い方を誤れば重大な事故につながる可能性があります。
新しいルールを正しく理解し、実践することで、誰もが安心して道路を利用できる社会を作っていきましょう。特に事業者の方々は、従業員の安全確保と法令遵守の両面から、早急な対応が求められます。
この機会に、個人としても組織としても、自転車運転に関する意識と行動を見直してみてはいかがでしょうか。
こちらのブログで「自転車のヘルメット装着義務」についてもご紹介しています。
弊社でも“KITARO”というテレマティクスサービスをご提供しております。
2024年10月にリリースした「KITARO×モバイル」サービスでは、電源を持たない自転車等の車両であっても、スマホを介してリアルタイム位置情報を確認でき、過去の走行履歴も3年分追跡することが可能です。
気になった方はぜひKITAROサービスサイトまでお問い合わせください。
▽出典
[1]政府広報オンライン自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html